Services for individuals個人の方に向けた業務
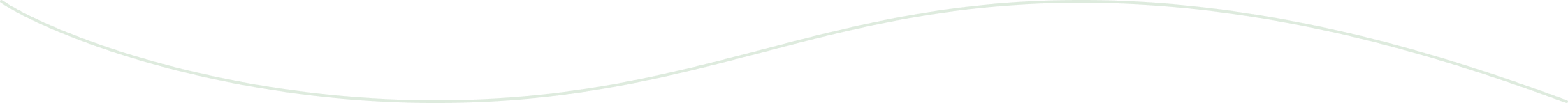
ご利用の流れFlow
-
01お問い合わせ
原則としてご来所の上、面談にてご相談をお聞きします。遠隔地にお住まいの場合や、時間外(夜間・土日)の対応が必要な場合は、Web会議(Zoom)による対応も可能です。
詳しくはこちら
ご相談には事前のご予約をお願いしております。まずは、お問い合わせフォームまたはお電話でご希望の日時をお知らせください。 -
02相談カードご記入
ご相談に先立ち、相談カードにご記入をいただきます。
※相談の際に関係資料をお持ちいただくようお願いすることがあります。詳しくは事前に説明させていただきます。 -
03ご相談
どんなに小さな疑問でも十分に耳を傾けて対応いたします。何でもお話しください。ご相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
-
04委任契約
ご相談の結果、ご要望に応じて御見積書を作成いたします。実際にご依頼をいただく場合は、別途、委任契約書の取り交わしをいたします。
業務内容のご案内Service
刑事事件
逮捕や起訴など刑事事件に巻き込まれた場合、ご本人やご家族にとって、被疑者・被告人の立場に置かれたときのご不安は、計り知れないものがあるかと存じます。そのようなご不安をできる限り小さくするために、早期の弁護士へのご相談が重要となります。裁判所に対する各種申立や捜査機関とのやり取り等をスムーズに進めることも可能となります。
起訴される前の段階では、迅速な対応により、身柄拘束の阻止・解放、不起訴処分の獲得などを目指します。また、起訴された場合でも、裁判で誤った事実の認定がなされたり、不当に重い刑を受けたりすることのないよう、適切な弁護活動を通じて依頼者の権利を守ります。
弁護士阿野寛之は、25年の弁護士経験で400件以上の刑事事件を扱ってきました。刑事手続の様々な局面でどう対応すべきかについての「引き出し」の数は、一般的な弁護士に比較しても引けを取らないという自負があります。
身体拘束された方のご家族・知人の方から接見のご依頼をお受けしたときは、原則として即日接見に赴きます。繰り返しになりますが、刑事事件はスピード対応が命です。是非ご相談ください。
対応例
1早めの出頭同行で逮捕を阻止
警察から呼出を受けた依頼者様から、「やったことは間違いない」、「逮捕は避けたい」というご相談を受けました。事件の内容について詳細な聞き取りを実施した上で、事件について認める旨の上申書を作成し、依頼者様の署名押印を得ました。その後、日程調整の上、依頼者様と一緒に警察署に出頭し、上申書を提出しました。これにより、逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがないことをアピールしました。その結果、依頼者様は逮捕されることなく、被害者と適切に示談し、不起訴処分を得ることができました。
2逮捕勾留されるも裁判所への
申立により身体拘束解放
逮捕に続いて裁判所から10日間の勾留決定を受けてしまった場合には、勾留決定に対する不服申立(法律用語では「準抗告」)をすることができます。申立が認められれば、勾留決定が取り消され、外に出ることができます。これまで10件以上の事案で、準抗告による勾留からの解放を得てきました。事案により、関係者の方から監督を約束する上申書をいただく等といった対応をスピーディに行う必要があります。豊富な経験に基づき、ご依頼から不服申立まで一気通貫で無駄のない対応が可能です。
3示談成立で不起訴処分へ
被害者がいる事件で、罪を認めている場合は、適切に被害弁償を行うことで不起訴処分を得られる可能性があります。依頼者様のご意向や、被害弁償の実現によって見込まれる結果等を踏まえ、被害者感情に配慮した適切な被害弁償交渉を行います。また、犯罪の成立を争う事件でも、被害弁償交渉を行うことはあり得ます(例えば、故意の傷害罪は「過失により負傷させた」として否認するが、負傷させたこと自体は間違いない場合等)。同様に、依頼者様のご意向や資力等を踏まえ、適切な示談交渉を行います。
検察官の処分決定に際しては、金銭的な補償の有無だけでなく、①被害者感情、②被疑者の反省状況が重視されることが多いです。①②とも、検察官に実態が十分伝わるよう努めます。
4起訴後の保釈で身体拘束解放
起訴された後は、保釈という制度があり、裁判所が保釈を許可した場合は、保証金納付を条件として、身体拘束から解放してもらうことができます。保釈請求に関しても、多数の取扱実績があります。保釈金立替業者(保釈支援協会等)をご利用いただく場合(親族・知人の方等のご協力が必要です)にも対応可能です。
5粘り強い弁護活動で逆転無罪
路上の痴漢事件で、被害に遭った女性が犯人を追うも見失い、たまたま付近にいた男性(依頼者様)を犯人だと思い込んだ、という事案でした。現場に何度も足を通い、再現ビデオを作成して証拠として出すなど、できると思われたことは全部やりましたが、1審では残念ながら有罪判決が出てしまいました。控訴審では、100ページ以上の控訴趣意書(控訴の理由を書いた書面)を提出し、原審の判決のおかしさをこれでもかと指摘した結果、控訴審で逆転無罪判決を得ることができました。
犯罪被害者支援
犯罪被害は、被害に遭われた方の心身に大きな傷を残し、ご本人やご家族にとって計り知れない不安や苦痛を伴います。突然の出来事にどう対応すればよいのか、法的手続や補償の問題で悩む方も多いでしょう。当事務所では、「寄り添う」姿勢を大切にし、犯罪被害者の方々が安心して前に進めるよう、全力でサポートいたします。
当事務所の弁護士は、長年にわたり、数多くの刑事弁護の経験を積み重ねてきました。その中で培った知識やスキルは、犯罪加害者の弁護だけでなく、被害者支援にも大きく役立つものと確信しております。刑事手続の流れや加害者側の心理を熟知しているからこそ、被害者の立場を的確に守り、最善の結果を追求することが可能です。実際に、ここ数年は、犯罪被害に遭われた方やそのご遺族・ご親族からのご依頼を受け、有効なサポートを実現することができました。
「依頼者様の正当な利益実現のために全力を尽くす」というのが、弁護士の使命です。被害者支援活動についても、依頼者様に誠実に向き合い、全力でサポートすることをお約束します。
対応例
1示談対応、加害者に対する
損害賠償請求
いうまでもなく、犯罪によって受けた精神的・肉体的な損害については、加害者に対して損害賠償請求が可能です。刑事手続が進む中で、加害者や弁護人から、被害弁償(示談)の申入れがなされることもあります。弁護士が被害者の代理人となり、加害者側に適切に対応します。また、刑事手続の過程で行う「損害賠償命令申立」や、民事裁判での損害賠償請求についても、必要なサポートを行います。
2刑事手続における支援
刑事弁護を経験する中で、多くの犯罪被害者の方から、「なぜこんな目にあったのかを知りたい」というお言葉を耳にしました。被害者の立場で刑事裁判に関わる際、どういう事件だったのかを知ることは、まさしく重要な権利です。検察庁・裁判所からの記録入手や、警察・検察との連携、ご本人に代わっての法廷傍聴などを通じて、そのような被害者の「知る権利」が実現されるようサポートします。
3被害者参加制度の利用
一定の重い事件については、「被害者参加制度」により、被害者が刑事裁判に参加し、意見を述べたり、証人や被告人に対し質問をすることができます。被害者参加制度では弁護士を選任することもできます。選任されれば、適切な処罰感情を裁判所に伝えることができるよう、弁護士が全面的にサポートします。
4被害者給付金・補償の請求
加害者からの賠償が十分でない場合や、加害者が特定されていない場合でも、犯罪被害者給付制度を利用して、国から一定の補償を受けられる場合があります。給付金の申請手続や証拠書類の準備を支援し、依頼者が可能な限り補償を受けられるようサポートします。
お金の請求・回収
ビジネスや個人間の取引において、売掛金や貸金などの「お金」を支払ってもらえないトラブルは、非常に大きな問題です。このような状況を放置しておくと財産的な損失が拡大するだけでなく、精神的なストレスも増してしまいます。当事務所では、お金の請求・回収に関する法的手続をサポートし、依頼者様の正当な権利が迅速に実現されるよう、お手伝いします。
対応例
1文書等による請求(裁判前)
多くのケースでは、まずは、弁護士からの文書・電話-・メール等により請求することになります。弁護士の名前を出すことで、相手によっては、「応じなければ裁判になる」、「本気で請求してきている」と受け取られ、相当の感銘力(心に響く力)が生じます。これにより、裁判手続を経ずとも任意の支払・回収に繋がることも少なくありません。
2支払合意書(示談書)の作成
請求書を送ると、相手が「一度には支払えない」、「分割で支払いたい」と言ってくることがあります。分割払いによる回収は、長期にわたる管理が必要となるため、請求側にとって経済的・心理的コストが生じますが、回収の実現のためには甘んじて受けざるを得ない場合もあります。依頼者様のご意向を十分に確認した上で、分割払いに応じる場合は、必要に応じ相手との間で支払合意書(示談書)を締結します。ご希望がありましたら、その後の分割支払についての管理業務(支払が滞った場合の催促を含みます)についても対応いたします。
3訴訟による回収実現
相手が裁判外の請求に応じない場合、請求を断念するか、訴訟手続等により請求をするかを選択していただくことになります(裁判外請求を行わず、いきなり訴訟をするケースもあります)。訴訟は、より強烈な感銘力を相手に与える手続であり、そこから回収に繋がる場合もありますが、相応のコスト負担が発生します。また、事案によっては、敗訴のリスクも考慮する必要があり、訴訟等に踏み切るには一定のご決断を要します。これらのメリット・デメリットをしっかり説明し、訴訟等に踏み切るかどうか適切にご判断いただけるよう努めます。また、訴訟等の手続の中で、裁判官が間に入り、双方の主張の間を取るような内容で和解(合意)により解決することもあります。
4差押による回収
裁判所が判決により支払を命じてもなお支払わない相手に対しては、強制執行(差押)を行うことが可能になります。差押とは、裁判所の強制力により、債務者が持っている財産を債権者に得させる、という手続です。差押手続を執ることにより、その財産を失いたくない等考えた債務者が、「支払うので差押を取り下げてほしい」と申し出て、全額を支払ってきた、というケースもあります。当事務所の弁護士は、財産の差押、特に給料等の債権差押に関しては、極めて多数の取扱実績があり、ご依頼いただいた場合は、迅速な対応が可能です。
5財産開示手続による回収
財産開示手続とは、強制執行ができる債権者からの申立により、裁判所が、債務者を呼び出して、持っている財産の内容を明らかにさせる手続です。債務者の財産を差し押さえようとする場合、債権者としては、相手(債務者)の財産を特定する必要があります(裁判所も、財産が特定されてないと、お金に換える等の手続を進めることができません)。相手の財産がどこにあるのか特定できないため差押ができず、「判決を 取ったはいいが 泣き寝入り」という事態が生じるケースも、残念ながら少なくありません。このような「泣き寝入り」を防ぐ手段となりうるのが「財産開示手続」です。財産開示期日で判明した財産を差し押さえたり、(裁判所に行くことを嫌がる)債務者から支払の申出がなされる等により、回収が実現することもあります。正当な理由なく欠席すると処罰(懲役または罰金)の対象となることから、欠席した債務者については、警察署に刑事告発を行うこともあります。刑事告発の結果、警察の捜査対象になった債務者から任意に支払がなされた、というケースも多数経験しております。財産開示手続に関しては、これまで100件以上の申立を行い、そのうち約7割のケースで全額または一部の回収につなげることができました(2024年10月現在)。取扱実績は他の同業者の追随を許さないという自負と自信がございます。メリットとコストを的確に説明させていただき、納得のいくご選択が可能になるよう、サポートいたします。
交通事故
交通事故は、突然の出来事であり、被害者・加害者ともに大きな精神的・肉体的な負担を伴います。事故後は、怪我の治療や修理の対応、保険会社との折衝など、慣れない多くの課題に直面します。こうした事態に適切に対処するためには、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが重要です。当事務所では、交通事故に関する豊富な経験と実績を活かし、依頼者一人ひとりに合った最適なサポートを提供します。交通事故でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
対応例
1保険会社との交渉
交通事故に遭うと、多くの場合、事故直後から相手方保険会社との交渉が発生します。あるときは「治療の一括対応(相手方保険会社による治療費の立替)を打ち切ります」と通告されたり、あるときは「代車費用は出せません」と拒否されたり、困った局面に出くわすこともあります。そのようなとき、弁護士が代理人として保険会社担当者と折衝します。これにより、お怪我の治療や日常生活に専念することが可能になります。
2後遺障害認定サポート
交通事故による怪我が完治せず後遺症が残った場合、その症状に応じた「後遺障害等級」の認定を受けることで、自賠責保険の保険金や損害賠償金を受け取ることができます。保険金や賠償金は、この等級に基づいて賠償額が決定されるため、正確かつ適切な認定が重要です。当事務所では、必要な証拠を揃え、後遺障害等級の適切な認定を受けるためのサポートを提供します。
3示談交渉・裁判手続き
ご本人が保険会社担当者と直接交渉した場合、本来認められるべき額よりもかなり低額の補償案を提示されることがあります。弁護士が介入することで、適正な金額による補償を受けられる可能性があります(ケースによりますが本人交渉の場合の数倍になることもあります)。示談交渉では、早期解決と適正額による解決のバランスを図りつつも、依頼者様のご意向を最大限に尊重して方針を決定いたします。示談で解決できない場合は、訴訟手続のほか、日弁連の示談あっ旋手続や交通事故紛争処理センターの利用も視野に入れながら、手続を選択していきます。いずれの手続においても、依頼者の正当な利益の最大化を第一目標として、過失割合や損害に関する主張立証を粘り強く行います。
4弁護士費用特約によるご依頼
事故に遭われたときは、必ず、ご自身やご家族が「弁護士費用特約」(弁特)に入っておられるかご確認ください。弁特は、自動車保険やその他の損害保険で特約として付帯していることが多いです。弁特があれば、交通事故やその他不慮の事故でお怪我をされたり、お車や持ち物を壊されたりした場合、弁護士に依頼する際の費用の全額(または大部分)が保険金として支払われます。当事務所では、弁特ご利用によるご依頼も可能です。お気軽にご相談ください。
離婚・夫婦関係に関する問題
夫婦関係が破綻し、離婚を考える際、感情的なストレスに加え、財産分与、親権、養育費など多くの法的な問題が絡んできます。これらを適切に解決するためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。当事務所では、依頼者の権利を守り、最善の解決策を導くために丁寧なサポートを提供します。当事務所では、離婚問題や夫婦間のトラブルに関して、経験豊富な弁護士が依頼者に寄り添いながら、最適な解決策を提案します。離婚・夫婦の問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
対応例
1婚姻費用・養育費
未だ離婚が成立していない夫婦間では、より収入の少ない配偶者や、子どもと同居し育てている配偶者は、他方配偶者に対し「婚姻費用」を請求できます。また、離婚後、子どもの親権者となった親は、他方の親に「養育費」を請求できます。婚姻費用や養育費は、両親の収入額をもとに最高裁(司法研修所)が定めた基準により決まりますが、事案ごとの事情により増減が生じます。別居期間中の生活や、離婚後のお子様の生活を安定させるためには、適切な婚姻費用・養育費の支払・受取がなされることが大切です。依頼者様のご意向とお子様の利益を最優先に考え、最善の結果を目指します。
2親権・面会交流
離婚に際しては、父母のいずれか一方を親権者として定めなければなりません。離婚協議や調停・訴訟では、どちらがより親権者にふさわしいのかについて、深刻に争われることがあります。親権の争いが生じた事案についても、一定件数の事案取扱実績があり、主張立証の方法も含め、適切に対応するよう努めます。また、非監護親とお子様との面会交流については、お子様の健全な生育にとって有益かどうかという観点から解決を図るものとされています。ご依頼者様のご意向を確認しながら、事案に即した柔軟な解決を志向しつつ、ご要望に応じて、連絡調整や交流立会等の支援を行います。
3財産分与
結婚生活で築き上げた財産は、離婚時に公平に分割される必要があります。共有財産には、住宅や預貯金、株式、退職金などが含まれますが、どのように分割するかで争いになることが少なくありません。依頼者様の正当な権利を守れるよう、財産の調査・評価を行い、適切な財産分与の実現を目指します。
4慰謝料
離婚の原因が配偶者の不貞行為やDV(家庭内暴力)などの場合、慰謝料の請求が可能です。慰謝料の額や支払い方法については、法的に適切な主張が必要です。弁護士は、証拠を基に依頼者の正当な権利を守り、適切な慰謝料を請求します。
5離婚協議の代理
以上のとおり、離婚に際しては相手と協議して解決すべき課題が多数あります。弁護士にご依頼いただいた場合、これらについて、全て弁護士が窓口となり行います。また、離婚交渉に際しては、日常生活にわたる細々とした協議事項(例えば「○○の書類を送ってほしい」、「荷物をいつ取りに行ったらいいか」、「携帯電話の契約を解約してもらえないか」等)が生じますが、離婚係争中の相手方とこれらのやりとりをすることはかなりのストレスになります。これらの協議事項についても、弁護士が連絡調整を行い、「寄り添う」サポートを実践します。離婚交渉に伴う日常生活上の物理的・時間的・心理的負担の軽減を図ることができます。
6調停・訴訟手続
話し合いによる離婚(協議離婚)が実現しない場合、家庭裁判所での調停や訴訟を通じて問題を解決することになります。裁判手続には、本人または弁護士以外が関わることはできません。「不安だから友達に付いて行ってもらう」ということもできません。また、調停委員は必ずしも法律の専門家でないことも多く、そのような調停委員に適切に対応するには、弁護士の助力が不可欠となる場合もあります。弁護士は、調停や裁判の場でも、専門的な知識を持って依頼者を支援します。
相続・ご高齢の方に関する問題
相続問題やご高齢の方に関する法的な問題は、誰にとっても不安や心配を伴うものです。特に、家族間のトラブルや今後の生活について、何をどのように進めればよいのか、悩む方が多いのではないでしょうか。当事務所では、依頼者の不安に「寄り添い」ながら、安心して解決に向けたサポートを提供いたします。
相続は、親族間での意見の違いや複雑な手続きが原因でトラブルに発展しやすい分野です。弁護士は、遺産分割や遺言書作成などに関して、依頼者の立場を守りつつ、家族間の円滑な解決を目指します。
ご高齢の方が直面する問題も多様化しています。家族が遠方に住んでいたり、健康状態が不安定になったりすることで、日常生活や財産管理においてサポートが必要になることがあります。当事務所では、依頼者やそのご家族に寄り添いながら、安心できる解決策を提供します。
対応例
1遺産分割
相続が発生した際、遺産をどのように分けるかを巡って争いが起きることが少なくありません。弁護士は、依頼者の意向に寄り添いながら、法的に適切な解決策を提案します。争いを未然に防ぐため、適切な交渉を行い、公正で円満な遺産分割をサポートします。
2遺言書の作成
遺言書が適切に作成されていないと、相続時にトラブルが発生する可能性があります。弁護士は、依頼者が希望する相続内容を明確にし、法律的に有効な遺言書の作成を支援します。また、作成した遺言書の保管や、万が一の際に遺言執行者としてもサポートします。
3遺留分の主張
相続において、遺言書で不利な内容が記載されている場合でも、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる権利が認められています。弁護士は、遺留分の請求や交渉を通じて、依頼者の正当な権利を守ります。
4任意後見制度
任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を「後見人」として指定し、自分の財産や生活を守る制度です。弁護士は、この制度を活用して、依頼者の希望がしっかり反映されるようにサポートします。依頼者の意思を尊重しつつ、安心できる将来を準備します。
5財産管理や成年後見制度
判断能力が低下した場合、ご自身の財産管理や日常生活のサポートが必要になることがあります。弁護士は、成年後見制度の利用を通じて、依頼者が安心して暮らせる環境を整えます。財産の管理や契約の代理など、法律的なサポートを提供し、ご高齢の方の生活をしっかり支えます。
その他
当事務所の弁護士は、その他にも、以下の業務について取扱実績があります。
どうぞお気軽にご相談ください。
対応例
1B型肝炎給付金請求
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染された方は、病態に応じて、国から50~3600万円の救済給付金を受け取ることができます。給付金を受給するためには、必要資料(検査結果、カルテ等)を揃えて訴訟を提起し、厚生労働省が定めた救済要件を立証する必要があります。ご自身でこれらの資料を揃えるのは大変な負担ですが、弁護士にご依頼いただくことで、ご負担を大幅に軽減し、請求手続をスムーズに進めることが可能になります。給付金請求手続のご依頼に際して、着手金のお支払は不要です(実費はご負担いただきます)。
2不動産賃貸借に関する紛争
不動産明渡事件(明渡を求める側・求められる側双方)のご相談や、賃料増額(または減額)請求のご相談もお受けしています。
3名誉毀損・誹謗中傷問題
新聞社等マスコミへの過去記事の削除依頼、各種掲示板への投稿削除依頼等についても、対応実績がございます。お気軽にご相談ください。
お問い合わせContact
当事務所は様々なお悩みにしっかりとお答えいたします。
費用のお支払方法に関しましては、ご依頼者様の状況に応じて、
分割支払等にも柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

